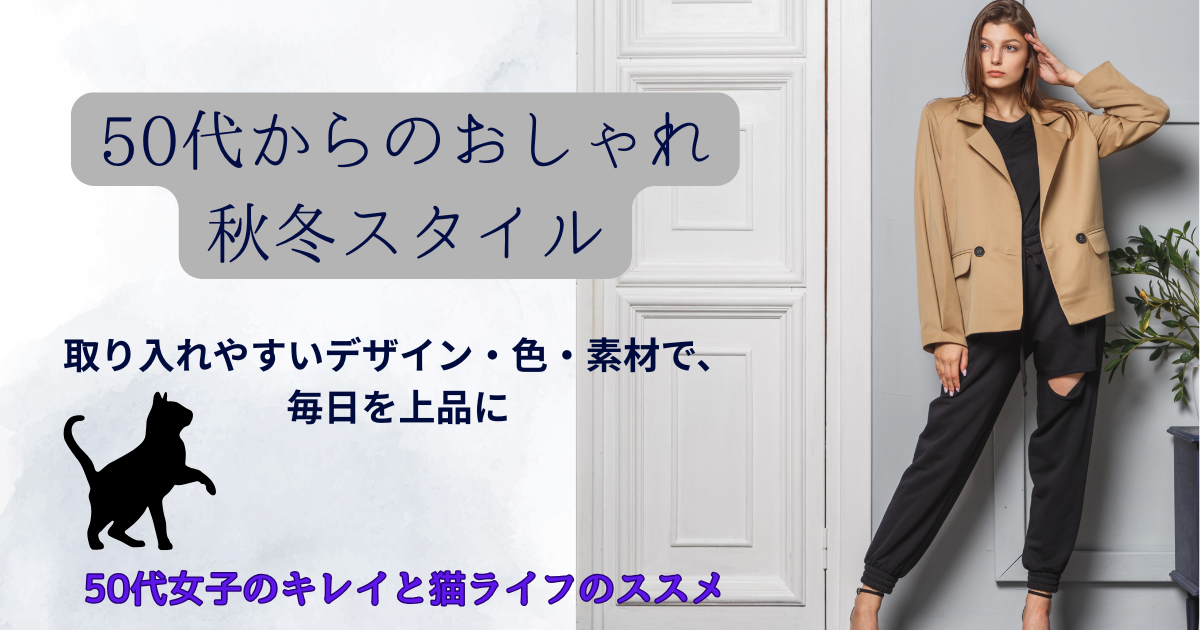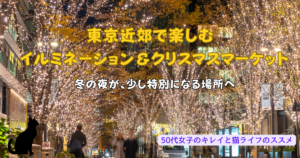「子どもは三人。手がかかって大変だったけど、みんな立派に育ってくれた。いまではそれぞれ家庭を持ち、孫も五人。あの人と『これからは少しのんびりしよう』なんて言っていたのに……」
老女の声が、ふっと途切れる。
「病気だったの。わたしが気づいたときには、もう遅かった。あっという間に……逝ってしまったのよ」
マスターは言葉を差し挟まず、ただ静かに目を伏せる。
「葬儀の後も、しばらくは夢の中にいるようだった。けれど七回忌を終えて、孫たちが遊びに来てくれたとき……ようやく思ったの。わたしはまだ生きているって。けれど、心のどこかでずっと、もう一度だけ、あの人とデートがしたかった」
老女はいたずらっ子のように笑う。
「それでね、孫に教えてもらった女風をいろいろ調べて、納得してから利用したのよ。あの人の若いころに雰囲気が似ているセラピストにあの人らしい服をプレゼントして着てもらったの。そして、思い出の店でビフテキの食事をして、バーで語らって…
もう、ダンスホールはないけれど、ラウンジでチークダンスをして最後はハグをして別れた。もちろん浮気なんてものじゃないわ。ただ、あの人との時間を、もう一度だけ思い出したかっただけ」
「セラピストは、また指名してほしいって言ったけど、わたしははっきり断ったの。もう二度と会わない。だって、あれは一度きりの追憶だから」
老女はカウンターに置かれた手をぎゅっと握る。
「そう遠くない未来に、わたしはあの人のもとへ行くでしょう。そのときにこう言うのよ。『わたし、浮気しちゃったわよ。あなたも若いころしたわよね?わたし、知っていたのよ』ってね」
老女は可笑しそうに笑い、そしてふとマスターの横顔を見た。
「あなたは、進めないのね」
マスターの手が一瞬止まる。だがすぐに穏やかに微笑み、問いかけた。
「……コーヒー占いをしてみますか」
老女は嫣然と微笑み、「ぜひ」と答えた。
トルココーヒーの残滓がカップの底に模様を描く。マスターはしばらく見つめ、静かに口を開く。
「秘密、です」
老女は声を立てて笑った。
「秘密ね。それが一番似合ってるわ、今のわたしには」
「楽しい夜の最後の締めくくりにピッタリだったわ。ありがとう。」
老女は席を立ち、ドアに向かう途中でハンキングチェアにいる空に気づく。
「あら、あなたにも待っている人がいるのね。」
そういって、カランとカウベルを鳴らしてドアを開け少女のような足取りで老女は出て行った。
外から、スルっと夜気が入り込み、一瞬、カフェの中の空気を新しくさせる。
カフェの灯は変わらず温かかった。