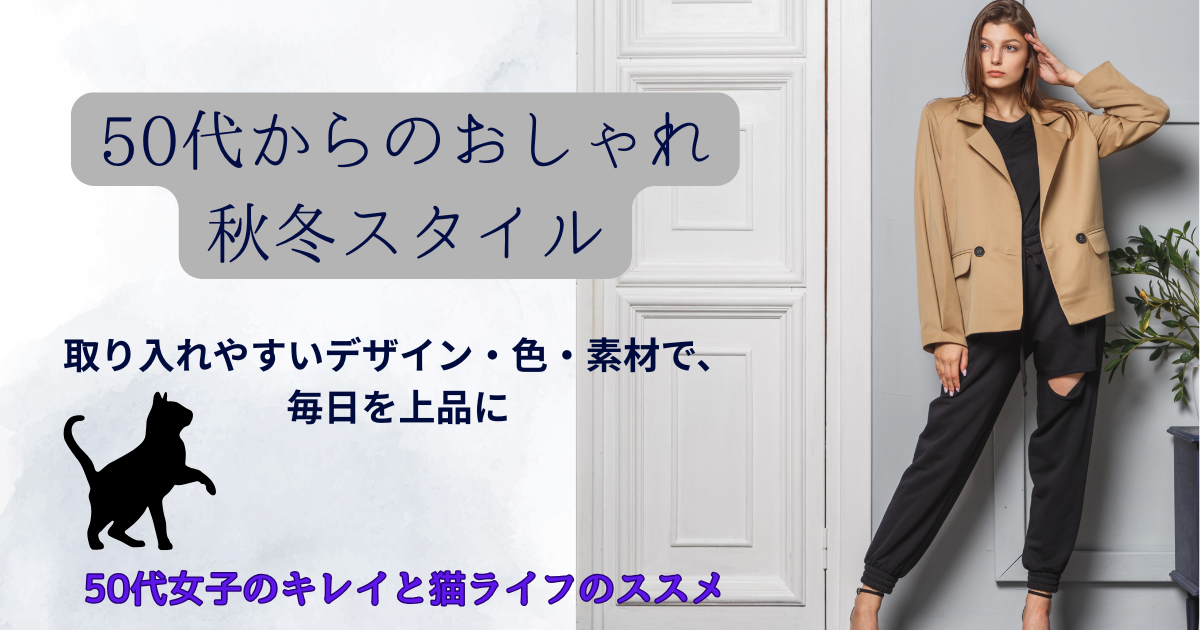カップに残る湯気を見つめながら、彼女のスマホが静かに震えた。画面に表示された名前を見て、胸が一瞬ざわつく。元カレだ。
店の外に出て、石畳の冷たい空気を胸いっぱいに吸い込む。路地の角で立ち止まり、深呼吸してから通話ボタンを押した。
「もしもし」柔らかな、少しだけ懐かしい声。あの日と同じ響きが耳に触れる。彼は短く近況を話し、そして言った。「時間ができたら会おうよ」
その一言に、胸の中に灯っていた小さな揺らぎが大きく膨らむ。彼の声にときめきが蘇り、頭の中にあの頃の情景が鮮やかに戻る。だが同時に、今の生活の輪郭もはっきりと思い出す。夫の顔、仕事場での自分、夜に洗い物を分担する手つき。
少しの沈黙のあと、彼女は静かに言った。「ごめんなさい。もう会えない」
会う約束を流すこと。その判断は、鼓動の早さとは別の場所で行われるものだ。電話の向こうの沈黙が一瞬だけ広がった後、彼は理解するように「そうか」と呟いた。
通話を終えた彼女は、スマホの番号表示を確認し、震える指で電話帳を開いた。画面の中の名前を見つめ、ゆっくりと『削除』を選ぶ。数字が消える音は聞こえないが、その所作は彼女の内部のひとつの区切りになった。
路地に戻ると、街は穏やかに動いている。深く息を吸い、彼女は夫に電話をかけた。呼び出し音が繰り返される間、胸の中で小さな決意が育っていく。
「今日は何時に帰る?」彼女は普段通りの明るさで問いかけた。「ちょっと、話したいことがあるんの」
短い会話の中で、夫は驚きながらも「わかった」と答えた。約束ができた。彼女はそのまま店へと足を速める。カフェの扉を開けると、中の温度がふっと包み込むように戻ってきた。
カウンターに戻ると、マスターは静かにうなずいた。ジェズヴェのそばに戻されたデミタスカップには、まだ飲み残しの琥珀色が揺れている。彼女は椅子に座り、残りの一口をゆっくりと味わった。
苦味が舌に残り、そこにスパイスの柔らかさが重なる。ひとくち、またひとくち。コーヒーの上澄みを味わうたびに、胸の奥のもやが少しずつ溶けていくような感覚があった。
「コーヒー占いをしてみますか?」
マスターは女性のカップをやさしく手に取り、ソーサーに載せてひっくり返す。少ししてから、粉の跡が描く模様を静かに覗き込む。
「結果は――『あなたが決めること』と出ています」
その言葉は重くもなく、軽すぎもしない。むしろ、まっすぐな真実だった。運命でもなく、他人の意見でもなく、自分自身の意思に帰ること。彼女は目を細め、ふっと笑みを漏らした。
「まだ、どうなるかわからないけれど、しっかり彼と話し合って後悔しても、失敗しても、逃げないで受け止める。そう決めます」だって、私は一度、逃げているのだから…
彼女の声は静かだが確かだった。マスターはにこりと頷き、何も余計な言葉を添えなかった。その微笑は、祝福にも見え、見守りにも見えた。
カップをそっと元に戻すと、残った温もりが指先に伝わる。彼女は立ち上がり、コートの襟を正した。出口に向かうとき、ハンキングチェアで静かに揺れる〈空〉に目をやり、小さく身をかがめて囁いた。
「君も大丈夫」
その一言は、まるで自分自身へ向けた呪文のようにも聞こえた。空は目を細め、わずかに微笑んだように見えた気がした。
「ごちそうさまでした」彼女は深く一礼して、颯爽とした足取りで路地へと出ていく。後ろ姿を見送るマスターの顔は温かく、店内にはトルココーヒーの余韻がゆっくりと漂っていた。
その日、選ばれたのは「向き合う」ことだった。答えはまだこれからだが、彼女は自分で選んだ道を、後悔も喜びも含めて歩いていくだろう。Café yakhtar の灯りは、また一人の決意をそっと見送った。