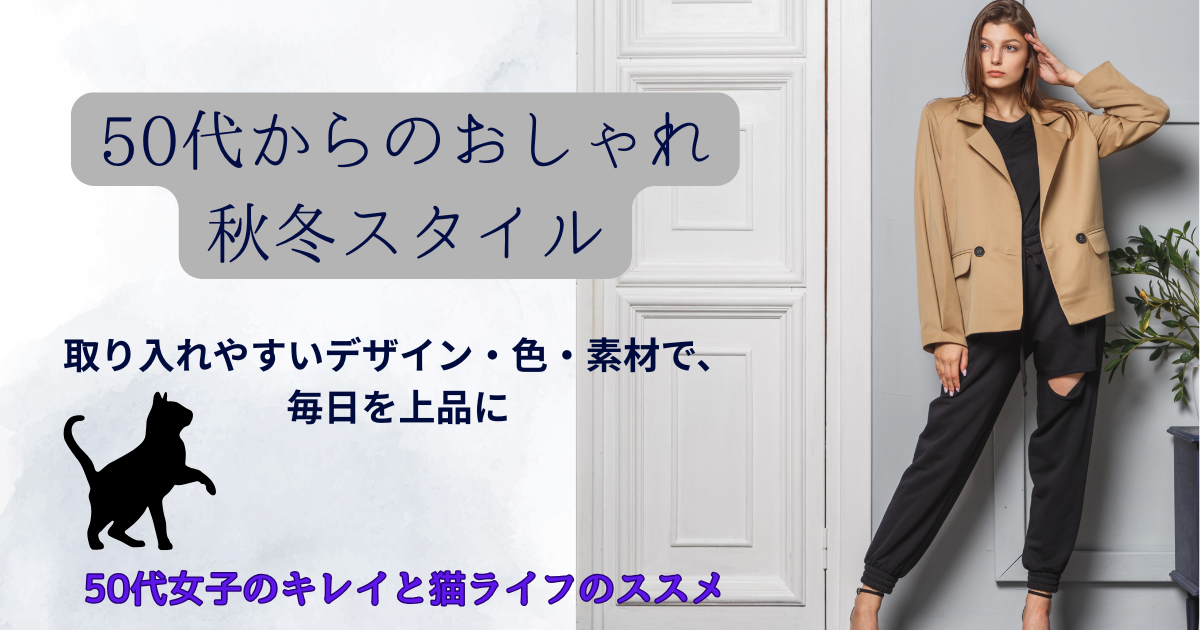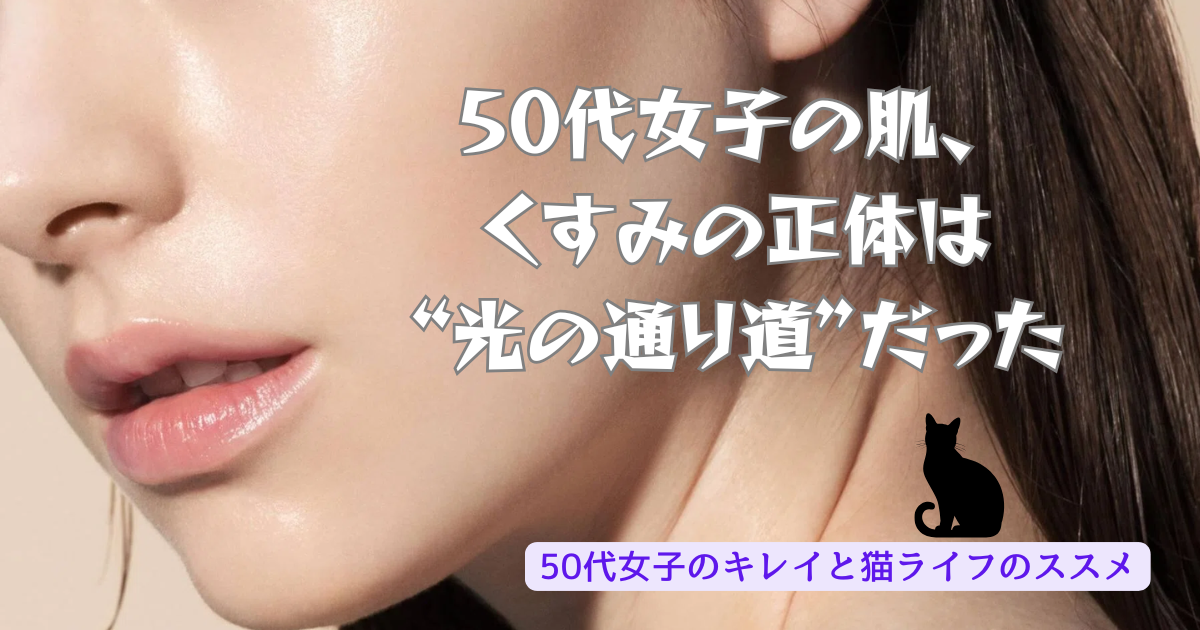雨上がりの路地は、石畳にほのかな光を反射させ、静かに佇んでいた。一本通りを入っただけで、異国の空気が漂う。カラン、とドアのカウベルが鳴る。
「いらっしゃいませ」
細くしなやかな指先がカウンターの奥で動く。店内は5つのカウンターのみ、そしてひとつだけのゆりかごのようなハンキングチェア。薄暗い照明はステンドグラスのランプと、異国を思わせる香りのするキャンドルに照らされ、洞窟の中にいるような、子宮のような安心感を与える。
初老の男性は息を呑んだ。カフェの名前、「yakhtar」はアラビア語で「選ぶ」という意味だと知っている。かつてトルコに駐在していた頃、妻と一緒に歩いたスークの熱気やスパイスの香りが、ふと蘇る。
「ここは、トルココーヒーとアイスコーヒーしかありませんが…」
マスターの声は耳触りの良い穏やかさに満ちていた。
男性は無言で頷き、静かに席につく。目の前にはトルココーヒーを作るための熾火と砂、銅の小鍋が揃っている。本格的なトルココーヒーを入れる店は、日本に帰ってきてから初めてだった。
「コーヒーが出来るまで、少し時間がかかります。七分ほどでしょうか」
その時間が、まるで導入のように、男性を昔の記憶へと誘う。トルコでの駐在時代の妻との日々、スークで買ったトルコ絨毯の重さに笑い合ったこと、二人で歩いた市場の熱気、甘く香るスパイス…。
妻は、スパイススークが気に入り、いつも連れて行ってくれとねだられたものだった。
男性は自然と、コーヒーを待つ時間の中で、妻の笑顔や声、小さなクセを思い出す。マスターの指先が静かに動き、銅の小鍋の中でコーヒーがじんわりと泡立つ。その手の動きの一つひとつが、異国の記憶と妻の記憶を呼び覚ます。
静寂の中で、トルココーヒー独特の香りが男性を包む。男性は無言で、思い出の中の妻と、まだ見ぬこれからの瞬間に心を預ける。