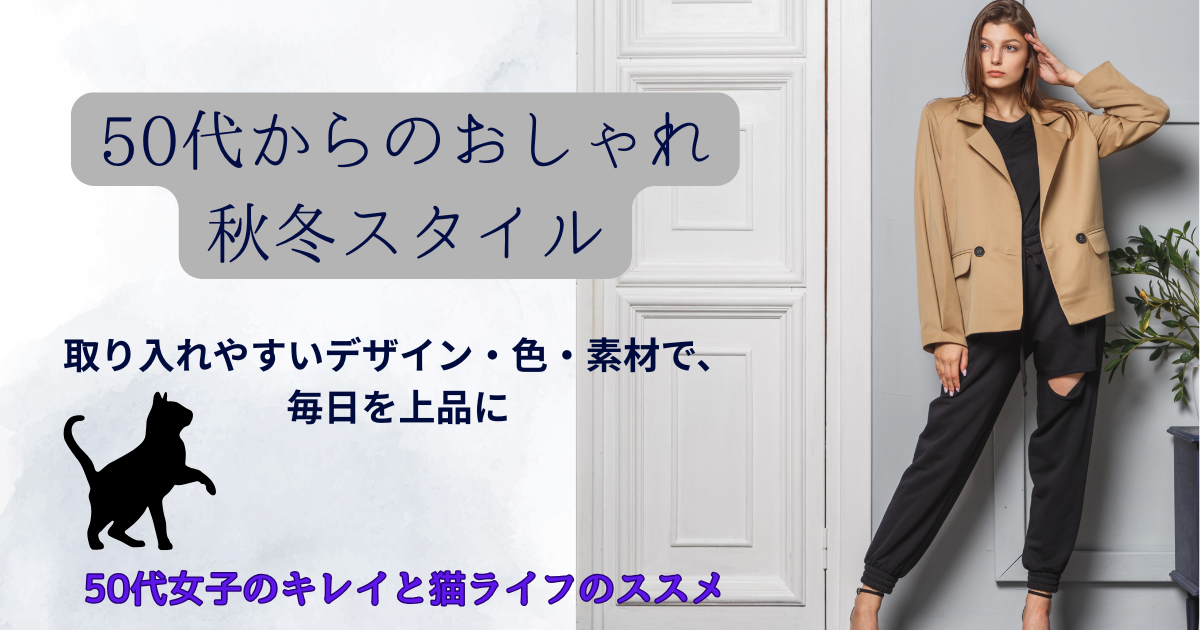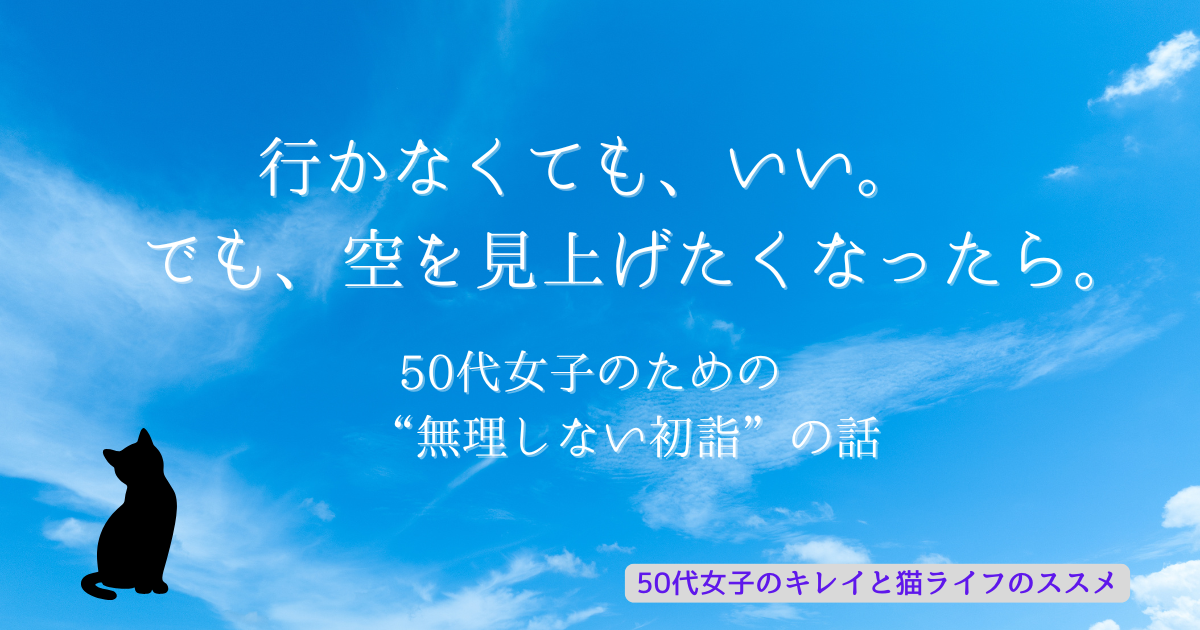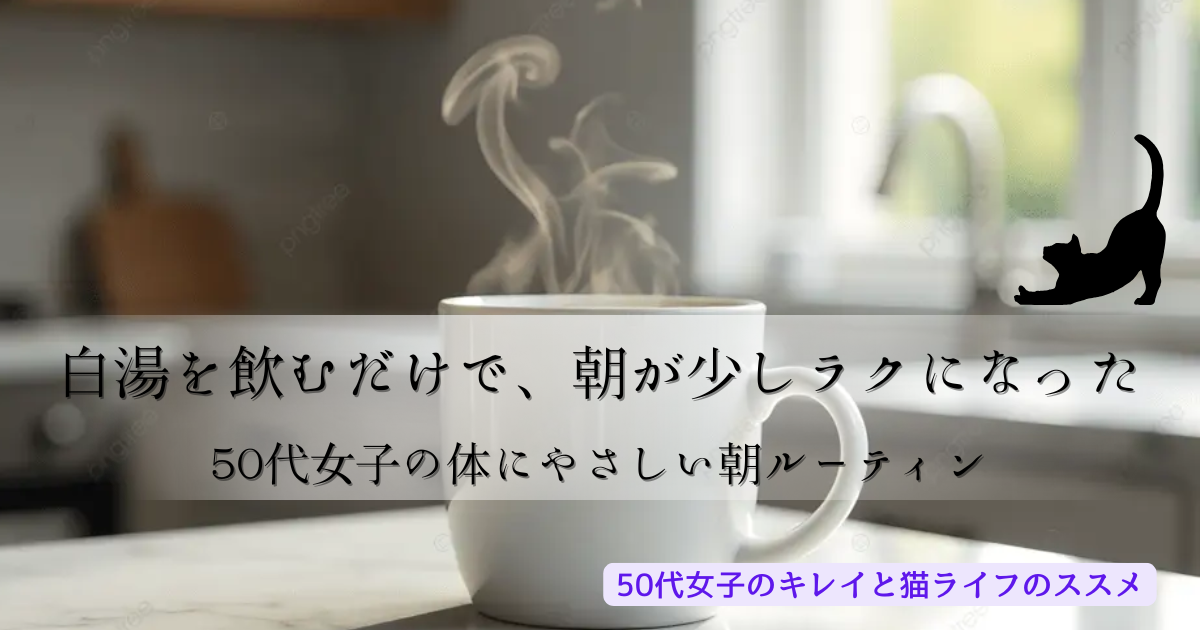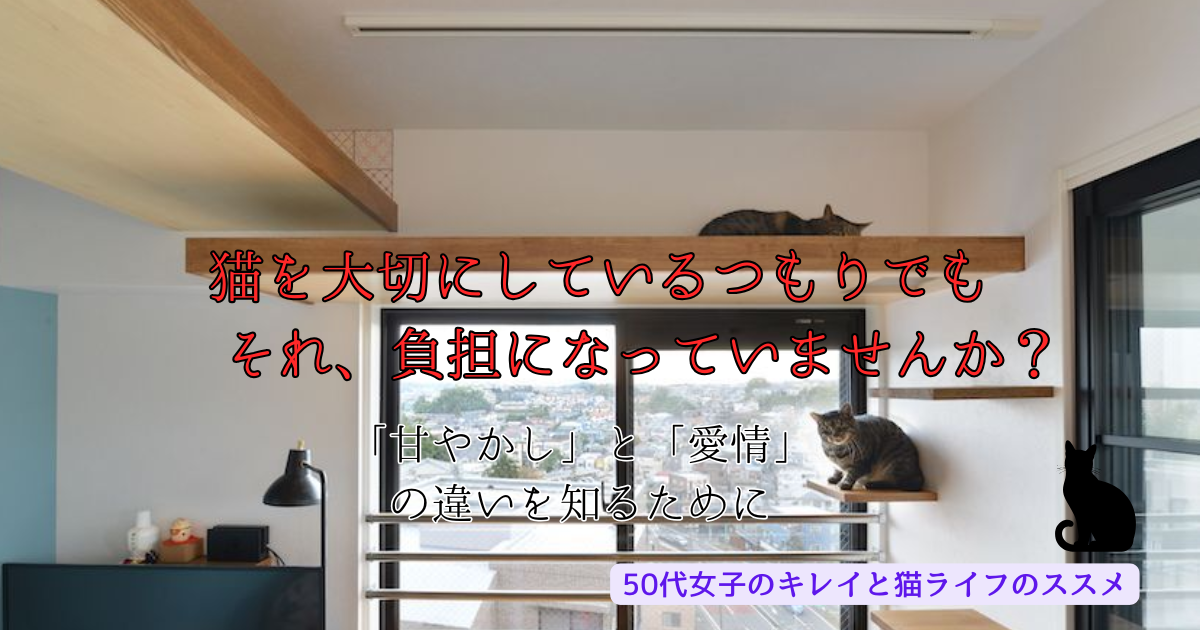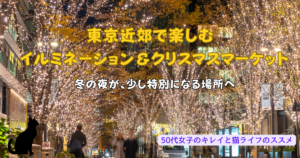マスターが差し出したデトックスウォーターを飲み干すと、胸の奥に滞っていたざらつきが少しだけ和らいだ気がした。グラスの中でハーブと檸檬がゆらめくのを眺めていると、不思議と時間がゆっくり流れていくように感じられる。
すこし気持ちが落ち着いた女子大生の心には、トルココーヒーへの興味が生まれてきた。「ねえ、マスター。トルココーヒーって、どんな味がするんですか?」
彼女が軽い調子で尋ねると、マスターは小さく頷き、棚の奥から銅色の小鍋を取り出した。
「これは ジェズヴェ と言ってね。粉に挽いたコーヒー豆と同じ量の砂糖、それに冷たい水、香りづけにカルダモンやシナモンを加えるんです。そして――」
マスターは、熾火で温められた砂に鍋をそっと沈めた。砂がざらりと音を立て、鍋のまわりを柔らかく抱き込む。その瞬間、店内の空気がさらに濃くなったように感じる。小鍋の中では、細かな泡が静かに立ち上がり、やがてふつふつと膨らみ、溢れそうになったところでマスターが砂を少し避けて落ち着かせる。その動きを、彼女は食い入るように見つめていた。
「これを二度、三度と繰り返して……ようやく一杯ができあがるんですよ」
「すごい……。まるで魔法みたい」
彼女の声には、さっきまでの苛立ちも自嘲もなく、純粋な憧れが滲んでいた。やがて小さなデミタスカップに注がれたコーヒーが、彼女の前に置かれる。表面には細かな泡が揺れ、黒褐色の液体が静かに深い香りを放っていた。
「粉が沈むのを待って、上澄みだけを少しずつ飲むんです」
「……いただきます」
カップを唇に寄せた瞬間、濃密な香りと苦みに甘さが絡み合い、胸の奥にじんわりと染み込んでいく。彼女は目を閉じ、短く息を吐いた。
「……少し落ち着きました。さっきまで、世界中が私を裏切ったみたいに感じてたのに。そして、私も裏切った側にいるって気持ちもあったの。」
言葉を選ぶようにしながら、彼女はゆっくりと語り出した。
幼稚園で初めてできた友達。それから引越しをしてしまったので会えなかった時間もあったけれど、高校で再会してからはずっと親友で、彼女にとって、何でも話せる大切な存在だった。
だが、同じ大学に進んで、同じ男性を好きになってしまった。でも、女子大生は、親友に話すことなく、男性と付き合うようになった。親友にも秘密の恋…ある意味、ちょっとした隠し事は恋愛への甘いスパイスの様だ。
だが、この彼には、束縛癖があることに気づき、このまま付き合っていくべきか悩んでいた時、親友が彼と仲良く腕を組んで歩いているのを見てしまった。
親友には何も言っていなかったのだから、親友は悪くない。悪いのはあの男だ。頭ではわかっているけれど、二人に裏切られたって言う気持ちを女子大生は抱いてしまった。
薄暗い妄想は、親友とあの男が二人で女子大生のことをあざ笑っているのではないか、親友は、女子大生とあの男が付き合っていたのを知っていて付き合っているんじゃないか…と答えの見つからない闇になり女子大生を覆っていく。
「それで、二人が私を裏切ったことが許せないって思っちゃったんです。だって、彼女だって私の気持ちを知っていたのに…きっと、二人して私のことを笑っていたんだって…そんな思いが膨らんで、どうしようもなくなって…だから私、親友と彼を呼び出して……二人と縁を切るって言ってしまったんです。」
カップを置く彼女の指先が、わずかに震えていた。
「今は、本当に親友は、私と彼が付き合っていたのを知らなかったんだってわかっているんです。だって、二人を呼び出して縁を切るって言ったときの親友の顔を見れば、誰だってわかります。わたし、間違ってたのかな……。どうするのが正解だったんだろう」「彼の束縛癖を親友に伝えるべきだったのかな」
女子大生は、あえて男の束縛癖を言わなかった自分の気持ちが暗い自分の本心ではないかと怯えていた。
思わずカウンターにうつぶせるようにして、抑えきれずに低く漏れる声でつぶやいた。
「あー……人生最低。もう、終わった……」
マスターは、無言でタブレットを差し出した。
不思議に思いながら画面を覗き込むと、そこに見慣れた名前が浮かび上がる。――付き合っていた男の名前だった。
『女子大学生、交際相手に刺され負傷』
「……うそ」
世界がぐらりと揺れた。視界が霞み、頭の奥が真っ白になる。だが、すぐにマスターの柔らかな声が耳を満たした。
「大丈夫ですよ。お友達は軽症です」
その言葉に、時間が世界が再び動き出した。胸を強く締め付けていた手が、少しずつほどけていくのを感じた。
「……行かなきゃ。すぐに」「行って謝らないと…私、わかっていたのに…」
席を立ち上がりかけたその時、テーブルの端でカップの中の黒い沈殿が目に入った。
マスターが微笑みながら言った。
「コーヒー占いを見てみますか?」
恐る恐るカップにソーサーを載せひっくり返した。コーヒーの粉が作り出した模様の中に、絡み合う二つの影が浮かび上がるように見えた。「再会と赦し」と小さくつぶやくマスター。
「……再会と赦しですか?」
「ええ。きっと、近いうちに」
胸に、熱いものが込み上げてくる。涙をこらえ、深く息を吸い込み、彼女はマスターに向かって丁寧にお辞儀をした。
「今度は、親友を連れてきますね!」
ドアに向かう途中、ハンキングチェアに丸まって座る少年のような影に笑いながら手を振り、「またね。きっと、もうじきだよ」と小さく呟いて、春のつむじ風のように駆け出していった。
その背中を見送りながら、マスターはゆるやかに微笑んだ。
「今日の選択は、安心を選ぶ日。きっと親友との再会も、良い方向へ向かいますよ」