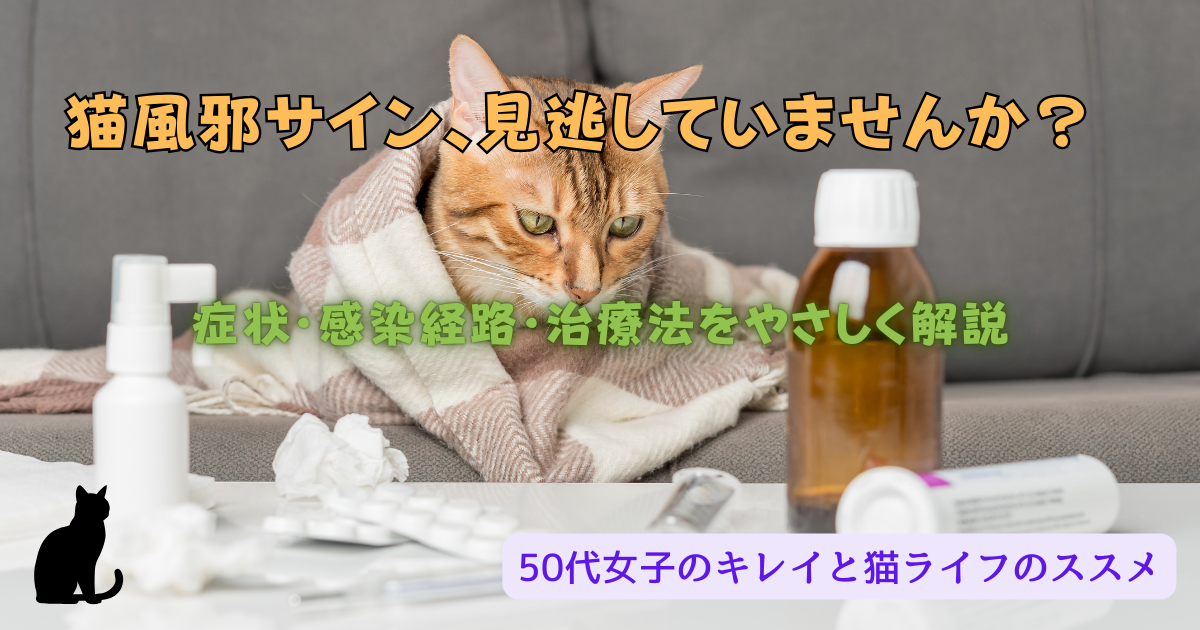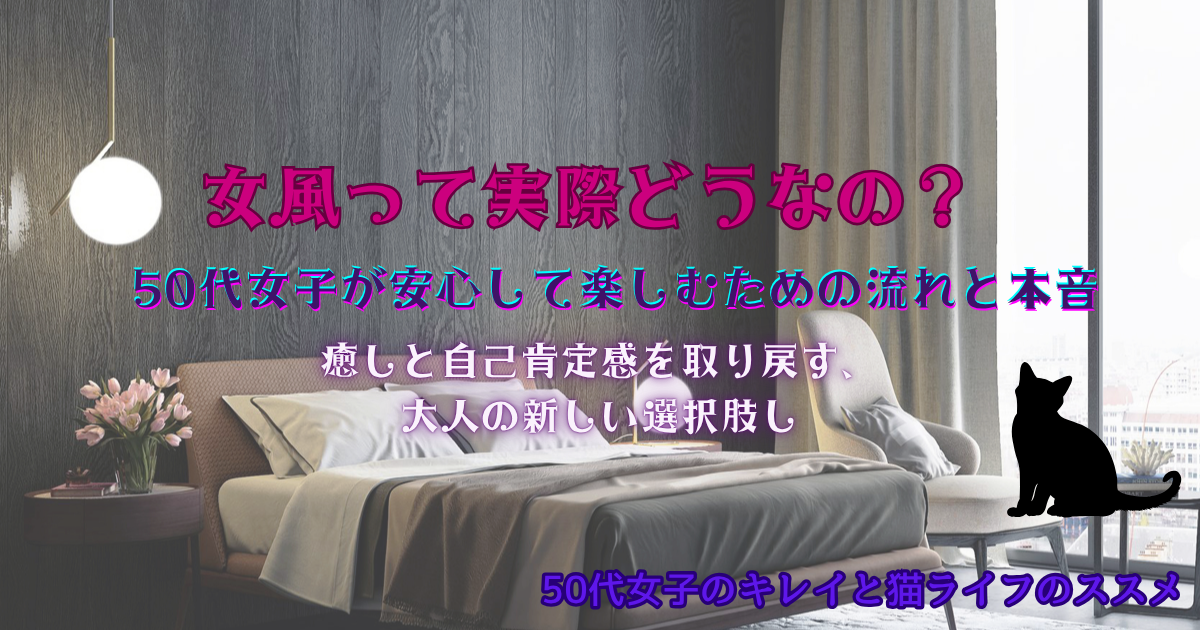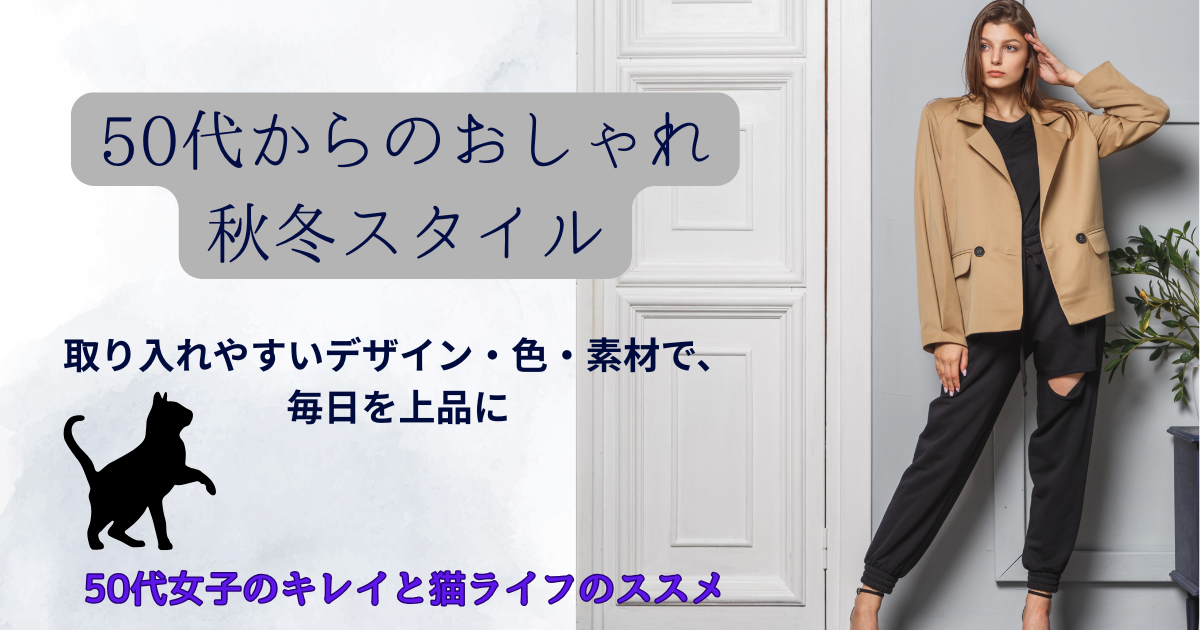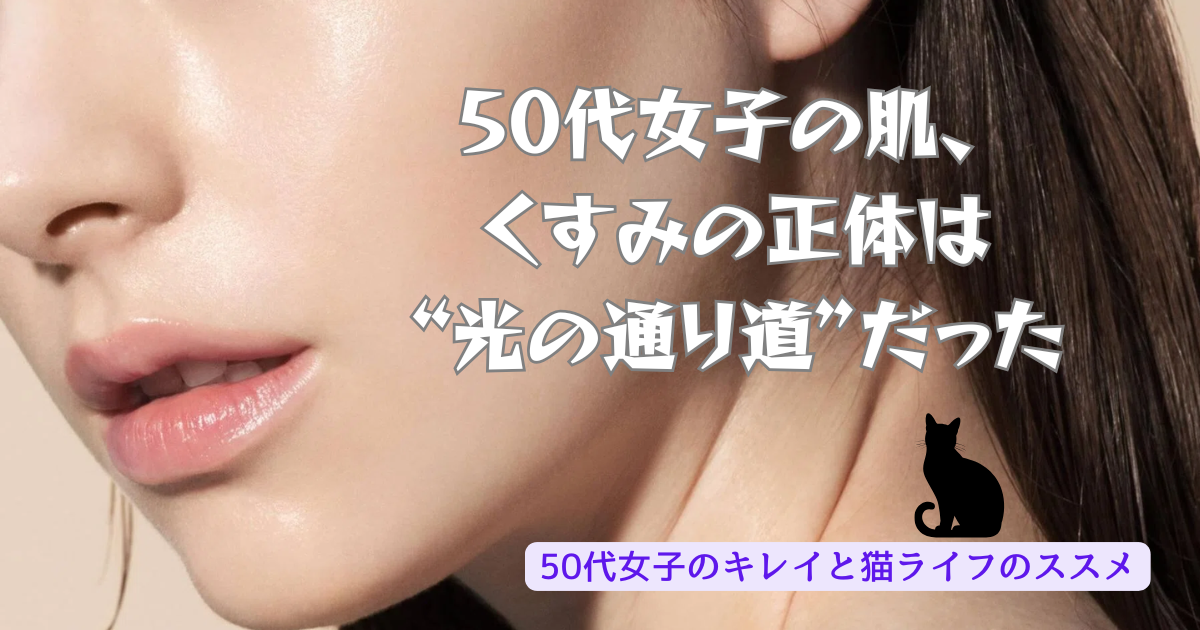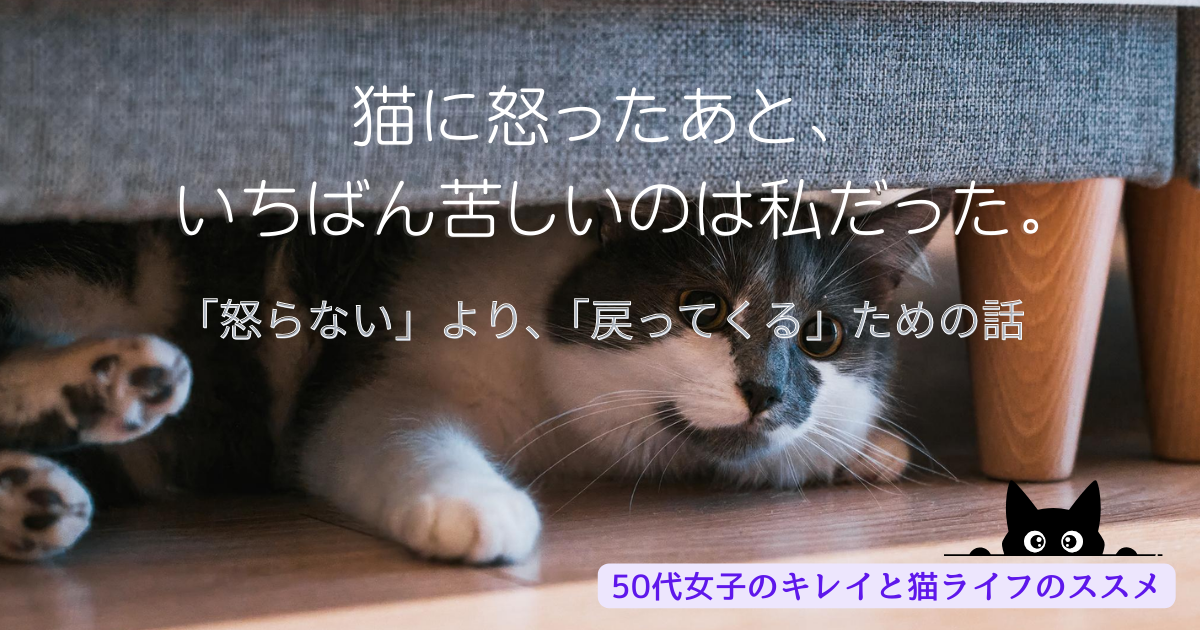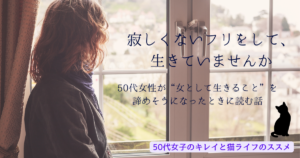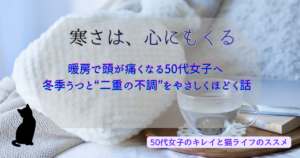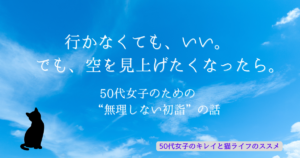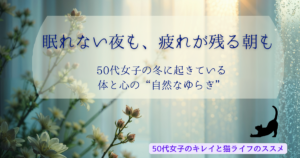おせち料理の由来って?縁起物のダジャレで選ばれた意味を知ろう
黒豆・数の子・伊達巻…おせちに込められた“願い”がわかる
こんにちは、ねこです。今日は日曜で連休の中日なので、ちょっとゆるっと読める内容にしました。
テーマは「おせち料理の由来とちょっと面白い意味」です。年末になるとスーパーやデパートで見かけるおせちですが、実は一つひとつに意味が込められているんですよ。
50代女子にもなると「知ってるよ~」って感じかもしれませんが、「へーっ」って思うこともあるかも…サラッと読んでみてください。
おせち料理ってそもそも何?

お正月になると当たり前のように食べている「おせち料理」ですが、 そもそもなぜお正月に特別な料理を食べるのでしょうか。
実はおせちには、家族の健康や商売繁盛、長寿など、たくさんの願いが込められています。
おせちは「節供(せっく)」に由来する言葉で、もともとは季節の節目に神様に供える料理でした。今のように三段重にしてお正月に食べる形式になったのは江戸時代から。元々は保存食が多く、日持ちする食材で作られていたのも特徴です。
おせち料理って、主婦(主にお料理を作る人)がお正月三が日に何もしないで済むようにって言う意味で保存がきくものになったって聞いたことがあります。でも、友達は、そのために2日位徹夜でお料理をしているので、果たして三が日が楽でも、やっぱり楽じゃないのではないかと思っています。
それに来客があれば、やっぱりいろいろ用意するのでキッチンに立つし…全然、主婦やキッチンに立つ人にとっては優しいお料理じゃないと思います。
また、昔は、三が日は火を使わない風習があったとか?(ちょっと記憶が定かではありませんが)
縁起物はダジャレで選ばれている?

黒豆・数の子・伊達巻などのおせち料理は、名前の語呂や言葉遊び(ダジャレ)から縁起物として選ばれたものが多いのです。例えば
- 昆布巻き:「喜ぶ」にかけて、家族みんなが喜びますようにという願い。
- 数の子:卵がたくさん並んでいることから「子孫繁栄」を意味。
- 田作り(ごまめ):小魚を田んぼの肥料に使ったことから「豊作・家運繁栄」を願う縁起物。
- 黒豆:「まめに働く・健康で過ごす」を願って。
- だし巻き卵:黄金色から「財運アップ」、丸く巻く形は「福を巻き込む」という意味。
こうして見ると、食べるだけで縁起をかつげる、という日本らしい文化の深さを感じますね。っていうか、江戸っ子ってダジャレ好きなんですよね。
その他の「へー」って思う由来
おせちには、まだあまり知られていない面白い由来や意味もたくさんあります。 「へぇ」と思える雑学を知ると、お正月の食卓がちょっと楽しくなります。
他にも、ちょっと面白い由来もいくつか紹介します。
- 紅白かまぼこ:紅は魔除け、白は清浄を表す。しかも半月型は日の出を象徴。
- 海老:腰が曲がるまで長生きできますように、という意味。
- 栗きんとん:金運アップの「金」にかけて、縁起物として親しまれています。
こういう意味を知ると、なんだかお正月の食卓がちょっと特別なものに感じませんか? 子どもと一緒に「これはどうして?」と話すのも楽しいですよ。
おせちは江戸っ子の粋が集まっている

おせち料理は、縁起・願い・遊び心が詰まった、日本らしい文化のかたまりです。
おせち料理はただの食べ物ではなく、それぞれに縁起をかけた意味やダジャレが隠れています。江戸時代の保存食としての役割から、今では家族みんなで楽しむ文化に変化しました。
昆布巻きで喜びを、数の子で子孫繁栄を願いながら食べる……そんな知識を少し知っているだけで、お正月がもっと楽しくなりますね。
今年のおせちは、ちょっとした雑学と一緒に味わうとさらに美味しく感じられそうです。作るほうは「勘弁してよ」って気分なんでしょうけれど…
ねこは、もう作りません。おせちは買います!
今日もお付き合いいただきありがとうございました。
楽しい連休をお過ごしください。
ではでは。